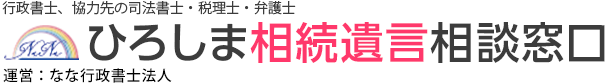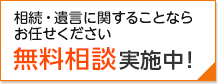遺言書がある場合の相続手続きと3種類ある遺言書の普通方式

遺言書は相続手続きにおいて非常に重要なものとなります。遺言書の有無によって手続きが大きく変わることもありますので、相続が発生したら何よりも最初に遺言書の存在について確認しましょう。また、ご自宅等で遺言書が見つからないときは、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認してみることをお勧めします。遺言書は作成者である被相続人の最後の意思なので、法にのっとって可能な限りその意思が尊重されたうえで相続を実行することが望ましいと言えます。
遺言書の普通方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。開封に際して、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行ってからでないと開封できません(法務局で保管された自筆証書遺言を除く)。公正証書遺言の場合は、そのまま手続きが進められます。
次に、自筆証書遺言、公正証書遺言の特徴と必要な手続きを確認していきましょう。秘密証書遺言については現在あまり利用されていないため割愛しますが、詳しくはひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせ下さい。
自筆証書遺言の場合
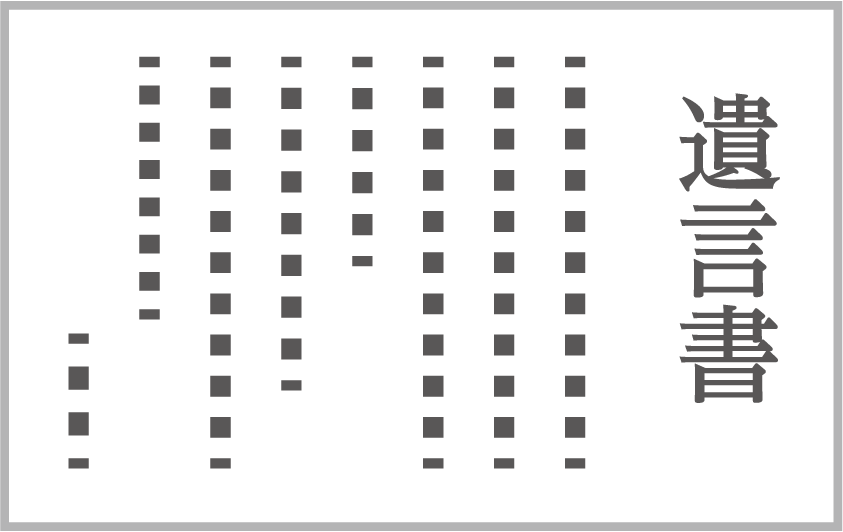
遺言書の作成者が自筆で全文および日付と署名を行い、押印して作成します。
作成場所、時間を問わず、自由なタイミングで作成できるため手軽ですが、ご自宅で保管していた自筆証書遺言は、方式の不備による無効、ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失、知らずに捨ててしまった、だれかが改ざんしたなどといったリスクが生じます。したがって、ご家族であっても遺言書を勝手に開封することは法律上禁じられています。
ご自宅等で自筆証書遺言を発見したらまず、家庭裁判所において検認の手続きをします。検認をせず勝手に遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せられるため注意が必要です。なお、法務局で保管していた遺言書に関しては開封時に家庭裁判所において検認を行う必要はありません。
また、もしも誤って遺言書を開封してしまった場合でも遺言書が無効になるわけではありませんので、そのまま検認の手続きをしましょう。
家庭裁判所での検認の流れ
- 家庭裁判所に検認に関する請求をする
- 家庭裁判所から検認日についての通知がくる
- 指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に立ち会う
- 遺言の内容および日付等を確認する
- 検認が完了したら、遺言書が返還される
- 遺言書の内容通りに相続手続きを進める
※ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書検認申立ての書類作成についてはパートナーの司法書士をご紹介いたします。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場で公証人と2名以上の証人が立会う中、ご本人の口述をもとにして公証人が作成する遺言書で、最も確実性の高い遺言方式です。公正証書遺言は、公証人が作成するため方式についての不備がないのはもちろんのこと、公証役場において保管されるため検認を行う必要はありません。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。
遺言書に記載の無い相続財産がある場合
遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、まず遺言書内に「記載のない財産の分け方」というような内容の文言がないか確認し、ないようであれば相続人全員が参加して遺言書に記載されていない相続財産についての遺産分割協議を行って、分割方法を決めます。
遺言書の内容通りにしなければならないのか
遺言書の内容に不服がある場合、遺言書の内容とは違った遺産分割をすることも可能です。
基本的には、被相続人の意思は尊重されるべきですが、相続人全員の話し合いにより、全員が合意のもとで、遺言書通りの遺産分割をしないという結論になった場合には、その旨の遺産分割協議書を作成することが出来ます。この場合、相続人全員が合意していることが重要で、一人でも遺言書の内容通りの遺産分割がいいと主張する場合には成立しません。
遺言書によって遺留分が侵されている場合
遺言書によって法定相続人の相続分が侵されている場合、一部の相続人は遺留分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言い、侵害している相続人や受遺者に対し、遺留分を請求する意思表示を行うことで、請求権を行使できます。
- 遺留分について
- 詳しくはこちら
相続手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
0120-770-563
【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00
当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703