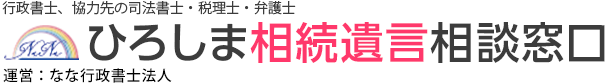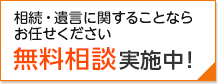行方不明の相続人がいる場合の相続手続き(失踪宣告について)

被相続人が遺言を残していない遺産相続の場合、相続人全員で遺産分割協議を行って、相続人全員が納得のいく分割方法で分配する必要があります。相続人のうち一人でも協議に参加していない場合は、残りの相続人で遺産分割協議を成立させたとしても、その分割協議は無効となってしまいます。
したがって、もしも相続人の中に行方不明の人がいた場合は、その行方不明の相続人抜きでは遺産分割協議を進めることはできないため、その行方不明の相続人の代わりに不在者財産管理人をたてて、行方不明の相続人が戻るまでその相続財産を不在者財産管理人に管理・維持してもらいます。ただし、行方不明になってから原則7年以上(戦災や天災に遭難した人は1年以上)経過している場合には、失踪宣告の手続きをすることも可能となるため、状況によって判断します。この、失踪宣告とは、行方がわからず生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
- 協議分割と流れについて
- 詳しくはこちら
失踪宣告
- 普通失踪
普通失踪とは、7年間生死が不明の不在者の失踪を宣告する(死亡したものとみなす)ものです。
ただし、7年間行方不明の状態が続けば自動的に死んだことになるわけではなく、利害関係人が家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをすることで初めて失踪宣告が認められ、行方不明者は「死亡したとみなされた状態」になります。死亡したとみなされる時期は、行方不明になってから7年間が満了した時点です。
- 特別失踪(危難失踪)
特別失踪(危難失踪)とは、火災や地震、戦地に臨んだ、沈没した船舶の中にいた等の死亡の原因となるような危難に遭った方が、それぞれ、その危難が過ぎ去ってから1年経過しても生死が不明の場合に認められる失踪宣告です。
普通宣告と同じく、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで初めて失踪が宣告されます。
死亡したとみなされる時期は、普通失踪とは異なり「危難が去った時」です。
失踪宣告後の相続手続きの流れ
行方不明者の失踪宣告が認められた場合の相続手続きの一例を見てみましょう。
死亡したAさんには子どもが3人います。遺言書は残されておらず、配偶者はすでに他界していて養子縁組もないので、3人の子どもB、C、Dさんが相続人となります。ただし、Dさんは10年前から行方不明で、子どもが1人(Eさん)がいます。
(例)
被相続人:Aさん
相続人:子であるBさん、Cさん、Dさん(10年前から行方不明)
上記のようなケースでは、Dさんは10年前から行方不明なので、不在者財産管理人を立てるのではなく失踪宣告を申し立てることが一般的です。失踪宣告が認められれば、被相続人Aさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの代襲相続人であるEさん(Aさんの孫)となります。このように、Dさんの失踪宣告が認められた場合には、代襲相続が起こることになるため注意が必要です。
失踪者が見つかった場合は取り消すことも可能

失踪宣告をしたあとに行方不明者が見つかった、または、死亡時期が判明し宣告した時期と違うことが証明できるといった場合には、失踪宣告を取り消すことができます。
では、失踪宣告を行ったことで受け取った相続財産や保険金はどうなるのでしょうか?
失踪宣告を認められた者が生きていた場合、相続人に引き継がれた財産は行方不明者に返還する義務がありますが、既に分割し手元にないものについての請求をすることはできません。保険金についても同様に、使ってしまった保険金は変換する必要はありませんが、手元に残っている分の保険金は保険会社に返還しなければいけません。
なお、失踪宣告の取り消しは本人又は利害関係人の請求により申し立てることができます。
このように、相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続手続きは複雑でわかりにくいことも多くありますので、不安な点やわからないことはひろしま相続遺言相談窓口の専門家にご相談ください。
ひろしま相続遺言相談窓口では、相続手続きの実績が豊富な専門家が、複雑な相続手続きもしっかりとサポートいたします。まずは初回無料相談をお気軽にご活用ください。
相続手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
0120-770-563
【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00
当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703